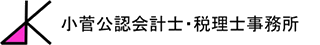「相続」と「遺贈」について
「相続」と「遺贈」はよく似た法律行為のため、混同している方も多いと思います。
今回はその違いについて解説したいと思います。
「相続」とは
相続とは、相続開始の日から亡くなった人(被相続人)が所有していた財産及び一切の権利義務を受け継ぐことです。
受け継ぐことができるのは、配偶者や子供など被相続人と一定の身分関係にある人(法定相続人)となります。人はいつか亡くなります。亡くなったときに相続は開始します。つまり、その人が死亡した日が相続開始日となります。
相続財産は、相続開始日に遡って法定相続人に所有権が移行します。
被相続人から相続人に引継がれる財産のことを「相続財産」といいます。
この相続財産ですが、土地・建物などの不動産、有価証券、現金、預貯金、自動車といったプラスの財産だけでなく、借金や負債、損害賠償責任などのマイナスの財産も相続されます。
ただし、その人だからこそ受けられる権利(一身専属権)や婚姻関係など、財産上以外の地位は相続の対象とはなりません。
「遺贈」とは
「遺贈」とは、亡くなった人(被相続人)の遺言に則り、法定相続人以外にその遺産の一部、または全部をゆずることを指します。
法定相続人にも遺贈することはできます。
遺贈する相手は、生前にお世話になった人といった特定の個人はもちろん、病院や教育機関、地方自治体やNPO法人などの人以外の団体や法人に設定することができます。
「相続」と「遺贈」の違い
「相続」と「遺贈」は財産をゆずるという意味ではよく似ていますが、細かな違いがあります。
まず、財産を受けとる対象が異なります。
「相続」
相続人が財産を受けとります。
「遺贈」
遺言に記されていれば、相続人でなくても受けとることができ、とくに制限はありません。人だけでなく、学校や施設など法人でも受けとることができます。
遺贈においては、遺産を贈る側の人を「遺贈者(いぞうしゃ)」と呼び、遺産を受け継ぐ側の人を「受遺者(じゅいしゃ)」と呼びます。
相続や遺贈と似たようなもの
「死因贈与」というものがあります。
こちらは、生前に自分の財産を誰にゆずるかを決めていることまでは同じですが、死亡を原因とした贈与契約という点が異なります。
契約なので、遺贈と違って受けとる相手とのあらかじめの合意が必要で、合意があれば法定相続人でもそれ以外の第三者でも、財産を受けとることができます。
遺贈も死因贈与も、死亡を起因として財産を受けとるという点では相続と同じですので、贈与税ではなく相続税がかかります。
第三者が遺贈を受けた場合には、法定相続人が納める相続税の2割増しの税金が課せられます。
また、遺贈や死因贈与で個人ではなく法人が財産を引き継ぐ場合には、相続税ではなく法人税がかかります。
第三者が遺贈によって受けとることになった財産が不動産の場合には、相続税のほかに不動産取得税が課されます。
一方、相続の場合には、不動産取得税は非課税です。
不動産を登記する場合には、登録免許税が必要になります。登録免許税は、法定相続人は0.4%ですが、受遺者が法定相続人以外の場合には2%と5倍かかります。遺贈された人が法定相続人である場合は、相続と同じ「不動産の1,000分の4になるという規定があるため、「法定相続人であれば1,000分の4」「法定相続人以外の人は1,000分の20」と考えてもよいでしょう。なお、相続登記は令和5年を目途に義務化が決定しており、登録免許税の軽減が図られる可能性がありますので、必ず最新情報をご確認ください。
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」がある
遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。
その内容や遺贈の方法によって大きな違いがあり、受けとる側や相続人にも大きな影響を与えるので注意が必要です。
包括遺贈とは
「包括遺贈」とは、遺産の内容を特定せずに全部、あるいは遺産全体の何割、何分の何というように割合によって与える遺贈を指します。
たとえば、「Aさんに自分の資産の2分の1をゆずる」というように遺言書には記載されます。
ただし、その遺産のなかには、借金などのマイナスの資産(負債)が入っている場合もあります。受けとる側は、その負債も割合に応じて併せて引き継ぐことになるので、注意が必要です。
特定遺贈とは
「特定遺贈」とは、あらかじめ遺産のうちの特定のものを指定して、与える遺贈のことです。
たとえば、「Aさんには不動産を、B法人には現金を、Cさんには株式を与える」というように遺言書には記載されます。
遺贈によって財産を受けとる人のことを「受遺者(じゅいしゃ)」と呼ぶと書きましたが、受遺者にも上で説明した包括遺贈で財産を受け取る場合と、特定遺贈で財産を受けとる場合では、権利や義務が違ってきます。また相続人と受遺者では考え方が異なります。それぞれの立場における考え方をご紹介します。
受遺者(じゅいしゃ)とは
「受遺者」とは、遺言者の遺言により財産を受け取る人のことです。
遺産を「相続」するのは相続人で、受遺者は相続人とは異なります。ただし、「包括遺贈」で財産を受けとる「包括受遺者」の場合には、相続人と同じ権利と義務があり、遺言者に借金などのマイナスの遺産がある場合にも、その割合に応じて引き継ぐことになります。
「特定遺贈」で財産を受けとる「特定受遺者」の場合には、受けとる財産があらかじめ指定されているので、遺産に関わる権利や義務は相続人とは異なってきます。
「遺言者」は個人、法人に限らず遺言によって自由に受遺者を決めることができます。また、遺贈を受ける側の「受遺者」は、なるための特別な条件はありません。たとえば、受遺者を第三者のお腹にいる胎児を指定することができます。遺言者である被相続人が亡くなった時に生まれていなかったとしても遺贈は効力を失いません。
ただし、被相続人が亡くなる前に受遺者が亡くなってしまった場合には、遺贈の効力は生じません(例外はあります)。
受遺者=相続人ではない
遺産を受けとるという点では受遺者と相続人は同じ立場ですが、「受遺者=相続人」ではありません。
相続人の範囲は、法律上決まっています。被相続人の配偶者はつねに相続人になります。
そして、被相続人の子どもや父母など、血のつながりがある人たちが相続人になれますが、その順位は民法で定められています。
第1順位は子どもで、その子どもが亡くなっている場合には、その子どもの子ども、つまり孫(直系卑属)が相続人になります。
それに対して、「受遺者」は遺言上で決められた人や団体のことです。遺言書で「孫のAに財産をゆずる」とあっても、まだ被相続人の子どもが存命で孫は法律で定められた相続人ではない場合には、Aさんは「受遺者」となります。ただし、遺贈されれば相続人であっても受遺者になります。
遺贈の放棄
遺贈は遺言者の一方的な意思表示なので、契約である死因贈与とは異なり、あらかじめ受遺者の受けとりの意思を聞いておく必要はありません。
したがって、もしも「包括遺贈」でマイナスの遺産も併せて受けとることになる場合などには、受遺者は遺贈の放棄をすることができます。
遺贈方法によって放棄の方法が変わるので、事項で詳しく解説します。
包括遺贈の放棄方法
「包括遺贈」で誰かの遺産を受けとることになったけれども、遺贈を放棄したい場合、自分に対して包括遺贈があった事実を知った時点から3か月以内に手続きをしないとなりません。もし、3か月が過ぎても遺贈の放棄の申述をしなかった場合には、受けることを承認したとみなされます。
包括遺贈の場合には、相続人と同じ権利や義務をもつことになるので、相続放棄と同じ手続きとなります。手続きは、相続放棄と同様に裁判所に申述をします。遺贈があったことがわかる書類と申述書を、遺言者が亡くなった住所地の管轄の家庭裁判所に提出します。受理・不受理の結果は、書面で連絡が来ます。
特定遺贈の放棄方法
「特定遺贈」を放棄する場合は、遺贈義務者である相続人か遺言執行者に対する意思表示だけで行えます。通常は、トラブルを避けるために内容証明で遺言執行者に送ります。また、包括遺贈とは異なり、「〇月〇日までに放棄の手続きをしなければならない」といった期間は定められていません。
ただし、受遺者が承認も放棄も意思表示をずっとしないままでは、相続人や遺言執行者などの利害関係者は遺産の分割ができないことになり、非常に迷惑します。そのため、遺贈義務者や利害関係者は、期間を定めてその期間内に遺贈を承認するか放棄するかを決めるように受遺者に催告することができるようになっています。受遺者が決められた期間内に回答をしなかった場合には、承認したものとみなされます。
遺贈のメリット・デメリット
では、生前贈与や死因贈与などではなく、「遺贈」という形をとることにメリットはあるのでしょうか。また、逆に遺贈することでのデメリットはあるのでしょうか。あるとしたら、どのようなことでしょうか。
ここでは遺贈のメリットとデメリットについて詳しく見ていきたいと思います。
遺贈するメリット
相続では、原則、法定相続人にしか自分の財産を遺すことができません。しかし、遺贈であれば、たとえば孫や兄弟姉妹など、法定相続人ではない親族にも財産をゆずることができます。遺言者が本当にゆずりたい相手を指定して財産を贈ることができるのです。また、生前にお世話になった人などを受遺者にすることで、自分の感謝の気持ちを伝えることができます。法定相続人以外の者の例を挙げると以下などがあります。
・婚姻関係がない内縁の妻や夫
・養子として迎えていない再婚相手の連れ子
・配偶者の両親や兄弟姉妹
・子供が存命である場合の孫
・可愛がっている甥姪やその子供
・お世話になっている第三者
・地方自治体やNPO法人
遺贈は個人だけでなく団体、法人も受遺者にできるので、支援しているNPO団体などに遺贈することで、自分だけでは成し遂げられなかった理想や思いを実現することもできるのです。もし、受遺者が受けとりたくない場合には放棄することができるので、一方的な押し付けになることもありません。
また、法定相続人以外に財産をゆずりたい場合、得てして財産分割のもめ事が起こることが多いものです。
このような場合、遺言の内容を非公開にしておくこともできます。
遺贈するデメリット
遺贈にはメリットもたくさんありますが、デメリットもあります。通常の遺贈では相続と同じく相続税がかかります。現金以外の遺贈の場合には、高額な相続税が負担となって受遺者がやむをえず遺贈を放棄することにもなりかねません。せっかく生前にお世話になった人や団体に気持ちを表そうとしたのに税金がかせとなって放棄されるのは残念ですし、受遺者も故人の感謝の意を税金が理由で受けとれないとなると、申し訳ない気持ちになります。
さらに、「遺留分」によるトラブルの恐れもあります。法定相続人には、法律で最低限相続できる割合がそれぞれの立場ごとに決められています。それが「遺留分」です。しかし包括遺贈によって全財産を特定の受遺者に贈るとされた場合、相続人は何も相続できなくなります。そのような場合には、遺留分を請求することができます。この請求を「遺留分侵害請求」といいます。
また、遺言書の書き方には一定のルールがあります。その遺言書のルールが守られておらず無効になると遺贈ができなくなることもあります。
遺贈における注意点
包括遺贈する場合、納得できない相続人から遺留分を請求されると、遺言者が考えていた割合で受遺者に財産をゆずることができないこともあります。そして、せっかく感謝の気持ちを示そうと思っていた受遺者を、相続トラブルに巻き込むことになりかねません。こうした争いは長びくことも多いので、なるべく避けたいものです。
そうしたトラブルが起きるリスクを減らすためにも、基本的には包括遺贈ではなく特定遺贈のほうが望ましいといえます。特定遺贈の場合にも、相続税などの税金が受遺者の負担にならないように配慮することが大事です。
遺言者として遺贈を行う場合には、遺言書を作成する前に遺留分が請求される可能性をあらかじめ考慮しておくとよいでしょう。遺留分を踏まえたうえで、誰に何をゆずるかを決めます。また、同時に受遺者に課せられる税金のことも配慮する必要があります。
また、遺贈には条件を付けることができます。たとえば、事業を継続することを条件に個人または法人に株式を譲ったり、家屋を維持することを条件に個人または団体に遺贈する場合などがあります。
ただし、注意したいのは、遺贈する相手に税金がかかる場合です。税金が負担にならないように配慮することが重要になります。
おわりに
遺贈と相続は似て非なるものです。
メリットも大きいですが、その分、見過ごせないデメリットもあります。遺言者としてお世話になった方や団体に遺贈したいなら、トラブルに巻き込むリスクをできるだけ減らすように遺言書を遺す必要があります。
また、ご自身や近しい人が受遺者になった場合に備え、まずは遺贈の流れを把握しておくことが大切です。そして、もしも受遺者になった時には、どういう種類の遺贈なのか、その内容を精査して、相続するかどうかをしっかり検討する必要があります。
相続・事業承継でお悩みの場合は、私共事務所にご相談下さい。
ご不明な点、ご質問等ございましたら【お問い合わせフォーム】までお気軽にご相談ください。
弊社でもさまざまなご支援をさせていただいております。サービス詳細についてはこちらへ
〇●企業という山を一緒に担げる舁き手のようなパートナーを目指します●〇
—————————————————————-
福岡で経営相談・アドバイスをお考えなら
小菅公認会計士・税理士事務所